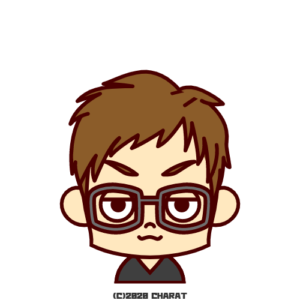こんにちは、元公務員のオウルです!
いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!
行政書士になるためには、一般的には行政書士試験を受験し合格することが必要です。
しかし、公務員として一定の勤続年数が経てば行政書士資格試験を受けなくても行政書士として登録できます。いわゆる免除になります。案外と知られてないんですね。
行政書士は、官公庁や役所に許認可書類の提出や手続きの代行、書類を業者や個人に代わって文書を作成したり申請したり、契約書などの作成が主な仕事です。
行政書士の仕事の幅はとても広く、行政書士が扱うことのできる書類の種類は1万を越えるとも言われているそうです。
役所や官公庁に提出する書類って、ぶっちゃけ煩雑ですし、手間がかかります。それを代行してもらうのが行政書士の仕事です。
公務員は市民と近い位置で働いているので、書類作成をはじめとした行政事務に携わる機会が多いです。公務員としての仕事は行政書士の仕事に似通っている部分も多いと思います。
今回は、公務員として働き続けると試験が免除される資格の種類について説明していきます。
行政書士の資格を得るためには
行政書士の資格を得るためには以下のいずれかの条件をクリアする必要があります。
- 行政書士試験に合格した者。
- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を有する者。
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、あるいは行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して17年以上(中卒の場合は20年以上)の者。
「行政事務20年以上(高等学校を卒業した者は17年以上)の経歴を有する者は試験免除」となっています。
公務員として高卒以上の場合は17年、中卒の場合は20年、勤務していた人であれば、無試験で行政書士になることができます。
行政書士試験は、仕事をしながらちょっと勉強する程度では合格できるようなものではありません。
行政書士試験は合格率が約10%と難易度が高い試験です。17年間あるいは20年間勤続さえすれば行政書士試験を受けなくて住むというのは、メリットであると思います。
ただしその代わりに、行政書士の資格を得るまでに、17年あるいは20年という長い年月をかかることを覚悟しなければなりません。
公務員が行政書士を取得するメリット
行政書士の資格を取得すると行政書士の事務所への転職、独立開業するチャンスが拓けるというのは大きなメリットでしょう。
公務員の年収は法律で決められているので、ずば抜けた年収をもらうことは限界があります。
しかし行政書士として独立開業すれば、公務員として勤務していた頃よりも大幅な年収増加が狙えますし、あるいは自分で働き方や働く時間を自由に決めることも可能になるなど大きなメリットがあります。
また、行政書士として事務所を開業し軌道に乗せるには、それなりの準備と経験が必要となります。
公務員は行政書士が作った書類を見る側の仕事をしているので、行政書士の扱う業務との親和性が高く、その業務経験が活かしやすいと思います。
公務員から転身した行政書士は、全くの未経験の状態から独立するよりも行政書士として成功する可能性が高いと思います。
退職後は、行政書士の事務所を開業する公務員も一定数います。
行政書士のお金の話、ぶっちゃけ儲かるの?
産業廃棄物対策課に務めている友人に聞いた話のことです。
産業廃物の収集運搬に係る許可の申請しに行政書士さんがよく職場に来られて、一件あたり8万〜15万ほどの料金をもらっていたそうです。
人脈さえあれば、行政書士って儲かるんですね。
産業廃棄物処理は自治体の許可が必要なのと改正などで手続きが煩雑なので、行政書士に依頼する業者が少なくないようです。仕事がなくなる心配もありません。
公務員時代に人脈や書類作成のノウハウを培って、独立開業をするのが、いいのかもしれませんね。
まとめ
公務員として17年間あるいは20年間勤務することで、行政書士資格試験が免除され、「行政書士」と名乗ることはできるようになります。
しかし、独立してやっていくにはやはり人脈が必要ですし、公務員時代にどんな実績を作ってきたかを証明していくのが重要になってきます。
公務員から行政書士に転身する予定がなくても、将来の働き方として、独立開業を選択肢の中に入れてみてはいかがでしょうか。